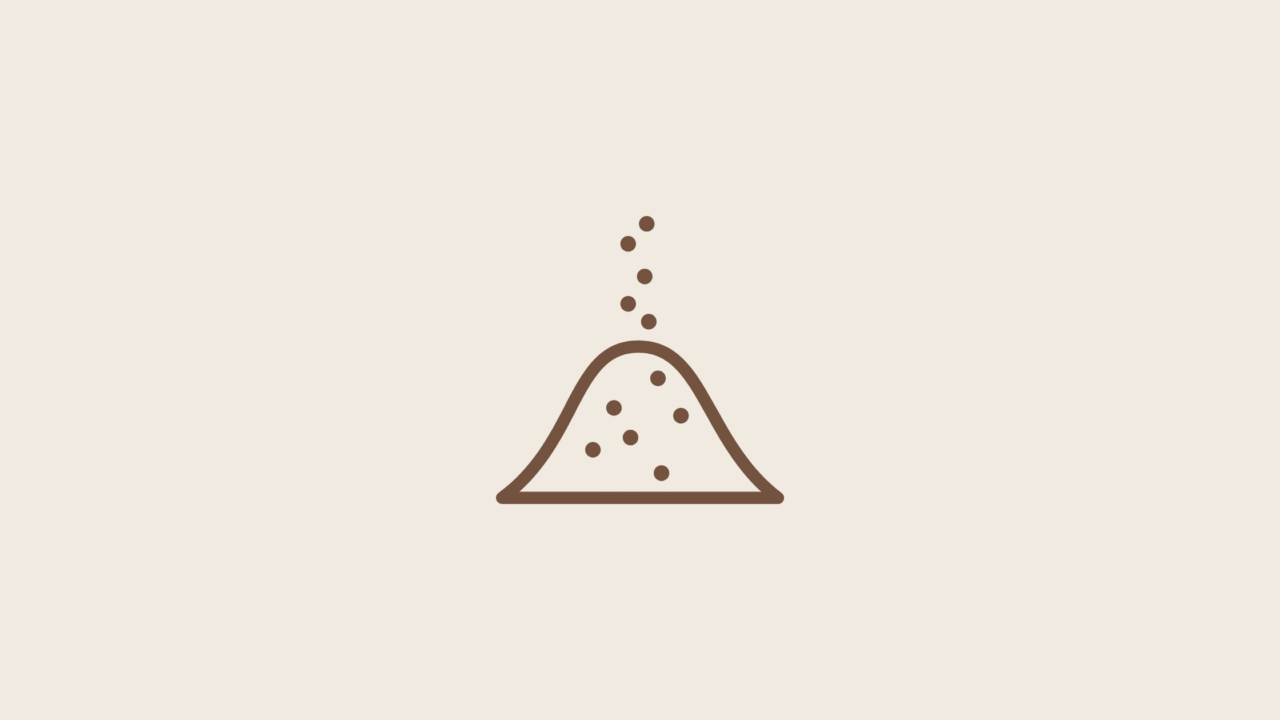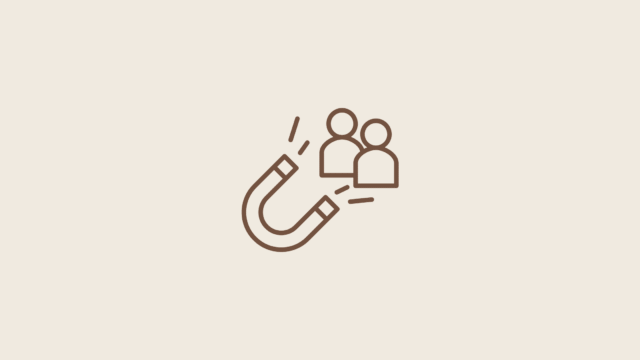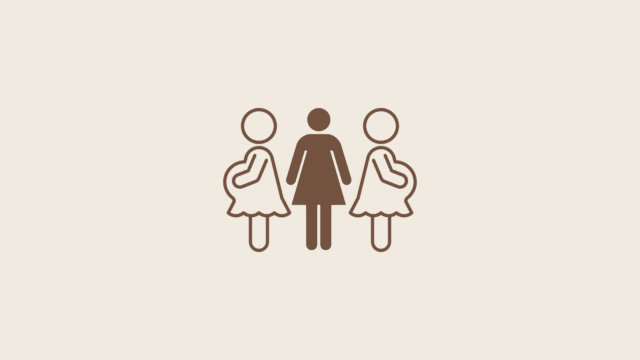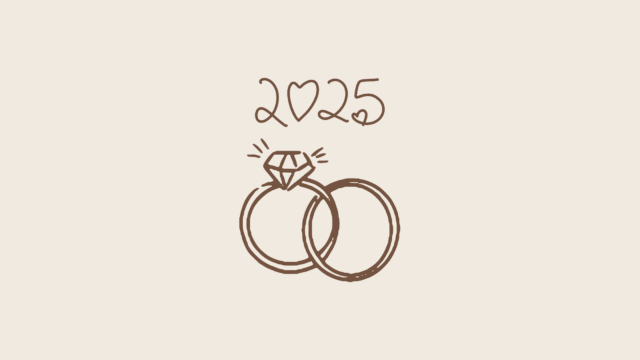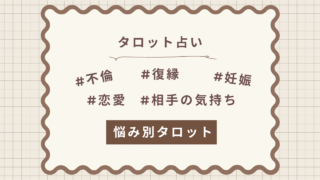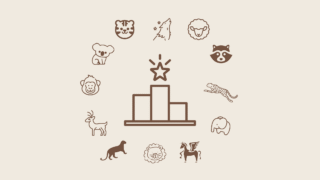「厄年って気づいたら過ぎていた…」
「厄払いのタイミングを逃してしまったけど、今からでも効果あるの?」
そんな不安を抱えている方も少なくありません。
本記事では、厄払いの時期を過ぎてしまった場合の対処法や、今からでもできること、さらには厄年をどう過ごすべきかについて詳しく解説します。
そもそも厄払いとは?
厄払いとは、厄年にあたる年齢の人が、災厄を避けるために神社やお寺で祈祷を受ける儀式のことです。
厄年は男性と女性で異なり、特に本厄は「大厄」とも呼ばれ、人生の中でも重要な節目とされています。
厄年の年齢や数え方については、ziredの厄年早見表で自分が該当する年を簡単に確認できます。
厄払いの時期はいつまで?
厄払いを受ける最も一般的な時期は、新年〜節分(2月3日頃)までの期間です。
これは旧暦における「立春(2月4日頃)」を一年の始まりとする考え方に基づいています。
しかし、厄払いは節分を過ぎても受けることが可能です。実際、多くの神社やお寺では年間を通して厄払いの祈祷を受け付けています。
厄払いの時期を過ぎたらどうすればいい?
時期を過ぎたからといって、厄年の過ごし方に「手遅れ」はありません。以下のような方法を取ることで、今からでも安心して過ごすことができます。
1. 思い立った時が最適なタイミング
厄払いに「絶対的な正解の時期」はなく、「厄年だと気づいた今」が行動するベストタイミングです。
ziredの記事でも「気づいた時に祈祷を受けるのが最善」とされています。
2. 神社やお寺に問い合わせて予約を
多くの神社では通年で祈祷を受け付けていますが、混雑やスケジュールの関係で事前予約が必要な場合もあります。
「〇〇神社 厄払い 予約」などで検索して、近隣の神社に問い合わせるのがおすすめです。
3. 自宅でのお清めやお守りも有効
神社に行くのが難しい場合、自宅でできるお清めの方法や、お守りを持つだけでも精神的な安心感につながります。
浄化用の塩や盛り塩、お札なども近年人気です。
厄払いができないまま過ごす場合の心構え
厄払いをしないまま厄年を迎えたからといって、必ず不運に見舞われるわけではありません。
以下のような意識で過ごすことで、厄年を穏やかに乗り切ることができます。
- 健康第一:定期健診を受けたり、無理をしない生活を心がける。
- 慎重な行動:転職・引っ越し・新規事業などの大きな決断は慎重に。
- 人との関係を大切に:家族や友人、同僚との関係性が支えになります。
- 感謝と謙虚な気持ち:日々の小さな出来事にも「ありがとう」の気持ちを。
厄年はむしろチャンスの時期?
厄年は、運気の停滞や変化を受けやすい時期とされますが、それは「自分を見つめ直す時期」「次の飛躍への準備期間」とも捉えられます。
大切なのは、ネガティブにとらえすぎず、自分にとって必要なことを見つけて実行することです。
関連記事
まとめ|厄払いの時期を逃しても大丈夫
節分を過ぎてしまっても、厄払いはまだ受けられます。
大切なのは、今の自分を大事にしようという気持ちと、何かしらの行動です。
「気づいたときが最良のタイミング」。この言葉を胸に、できることから始めてみましょう。
不安が和らぎ、心穏やかに過ごせるはずです。